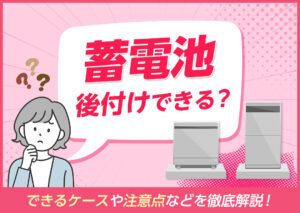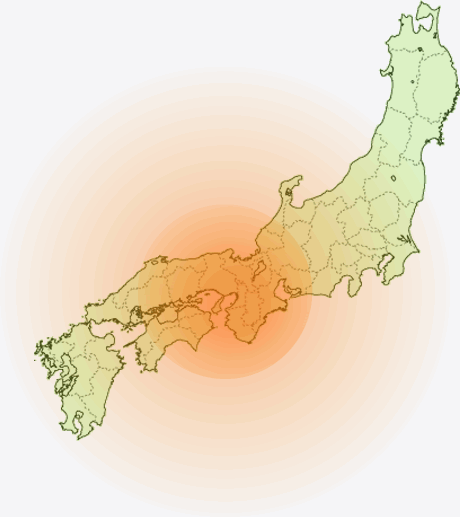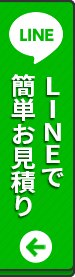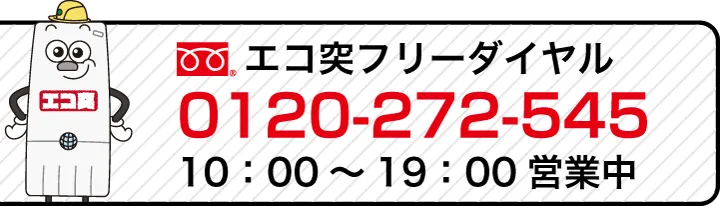蓄電池
2025/08/18
蓄電池で「元が取れない」って本当?理由やシミュレーション、元が取れるケースなどを解説
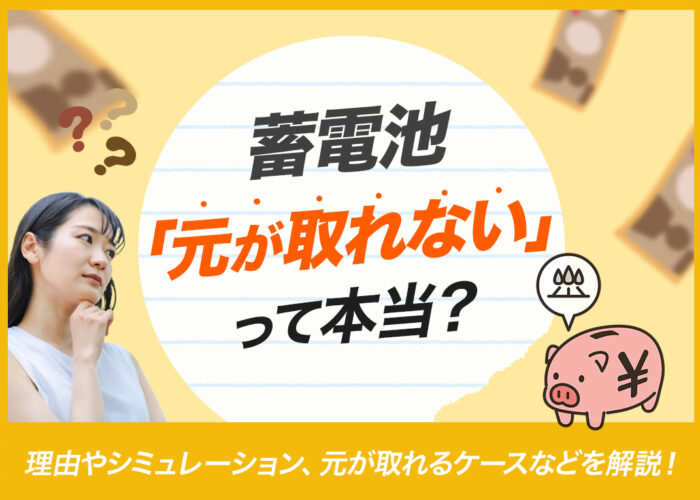
蓄電池を購入しようと調べると、「元が取れない」という意見や口コミを見かけることがあるかもしれません。
確かに、蓄電池は太陽光発電システムに比べて節電効果が高いとは言えず、単体で導入しても元が取れる可能性は低いです。
しかし、蓄電池を導入しても元が取れるケースはあります。
そこで今回は、蓄電池で「元が取れない」と言われる理由や実際の導入シミュレーション、元が取れるケースのポイントなどをわかりやすく解説します。ぜひ最後までご覧ください。
蓄電池で「元が取れない」と言われる主な理由

蓄電池で「元が取れない」と言われる理由は、主に以下のとおりです。
- 初期費用が高額
- 蓄電池だけでは節約効果が小さい
それぞれ、順番に解説します。
初期費用が高額
家庭用蓄電池の導入には、機器本体・設置工事・電気配線などを含めて100万〜200万円前後の費用がかかるのが一般的です。
三菱総合研究所の資料によれば、補助事業以外で家庭用蓄電池を導入する場合、設備費は15~20万円/kWh、工事費は2万円/kWh程度かかります(※)。
蓄電容量1kWhあたり22万円とした場合、蓄電容量5kWhの蓄電池を設置するための初期費用の目安は110万円です。
太陽光発電と併せて導入する場合はさらに高額になるため、「元が取れるかどうか」が不安視されやすい理由になります。
ただし、同資料では補助事業を利用できた場合の導入費用が、設備費は11.1万円/kWh、工事費は1万円/kWh程度です。
補助金制度の有無によって初期費用の負担は大きく変わるため、導入前に利用できないか確認しましょう。
(※)参考:三菱総合研究所「2024年度 定置用蓄電システム普及拡大検討会の結果とりまとめ(案)」
蓄電池だけでは節約効果が小さい
蓄電池は、家庭で使う電力を一時的に蓄えておき、必要なときに放電して使える装置ですが、単体では大きな節約効果を生みにくいのが実情です。
太陽光発電システムと組み合わせて利用すれば、昼間の余剰電力を夜間に活用することで買電量を減らせるため、節電メリットが高まります。
一方、蓄電池のみの場合は、電気料金が安い深夜帯に充電し、高い日中に使うことで節約を目指しますが、その差額は小さく、導入費用を回収するには時間がかかりやすいです。
例えば、関西電力の「はぴeタイムR」を契約している場合、電気量料金単価は次の表のとおりです。
| 区分 | 単位 | 料金単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 最初の10kWまで | 1契約 | 2409.40円 | |
| 10kWを超えて1kWにつき | 1kW | 416.94円 | ||
| 電力量料金 | デイタイム | 夏季 | 1kWh | 28.87円 |
| その他季 | 26.24円 | |||
| リビングタイム | 22.80円 | |||
| ナイトタイム | 15.37円 | |||
蓄電池だけを導入している場合、毎日午後11時~翌日午前7時のナイトタイムに電力を購入し、デイタイムやリビングタイムに消費することで最大13.5円/kWhの節約効果を得られます。
一方、太陽光発電システムと一緒に導入してれば、余剰電力を蓄えておき、発電できないリビングタイムやナイトタイムに購入する買電量を減らすことが可能です。
- 蓄電だけ…最大13.5円/kWhの節約効果を得られる
- 太陽光発電システムとの併用…22.80円/kWhや15.37円/の節約効果を得られる
経済性を重視するなら、太陽光との併用が前提といえるでしょう。
蓄電池だけ導入した場合に元が取れるかシミュレーション
太陽光発電システムを設置せず、蓄電池だけを導入した場合に元が取れるかどうか試算してみましょう。試算条件は以下のとおりです。
- 初期費用…110万円
- 蓄電容量…5kWh
- 電気料金…関西電力「はぴeタイムR」
蓄電池だけを導入する場合、電気料金単価が安い夜間に電力を購入し、単価の高い日中に消費して買電量を減らすことで節約が可能です。
仮に、関西電力の「はぴeタイムR」と契約している場合、ナイトタイム(深夜)の料金は15.37円/kWh、デイタイム(昼間・夏季)は28.87円/kWhのため、深夜に蓄電し、昼間に使用することで1kWhあたり最大13.5円の差額を節約できます。
毎日5kWh行った場合の年間の節約額は約24,637円で、初期費用110万円を回収するためには40年以上かかる計算です。
今回はシミュレーションのためデイタイム(その他季)や経年劣化による蓄電容量の減少などは考慮に入れておりませんが、蓄電池の寿命が10年~15年程度なことを考えると、蓄電池単体で元を取るのは現実的とは言えません。
元が取れるケース・取れないケースの違いとは?
蓄電池を設置して元が取れるケース・取れないケースの違いは、主に以下のとおりです。
- 太陽光発電システムの有無
- 日中と夜間の電力使用量のバランス
- 補助金の有無
それぞれ、順番に解説します。
太陽光発電システムの有無
蓄電池で「元を取る」ためには、太陽光発電システムの存在が大きなカギを握ります。
蓄電池単体では、夜間に電気を蓄えておき、日中の買電量を減らすことでしか節約効果を得られません。
しかし、太陽光発電システムを設置すれば、昼間に発電した電力のうち、使い切れなかった余剰電力を蓄電池に溜めておき、発電できない夕方以降や雨天時に活用することで、1日の買電量を大幅に抑えることが可能です。
例えば、日中の蓄電池に余剰電力を5kWh溜めることができれば、午後5時~午後11時のリビングタイム(生活時間)の22.80円/kWhを減らすことができます。
シミュレーション上では年間41,610円の節約効果を得られるため、蓄電池単体での運用と比べ、太陽光発電システムとのセット導入によって元が取れる可能性は高いです。
日中と夜間の電力使用量のバランス
太陽光発電システムや蓄電池は、1日の中で電気料金単価が高い時間帯に電力を買わずに済ませることで電気料金の節約を実現する仕組みです。
しかし、家庭ごとに異なる「日中と夜間の電力使用量のバランス」によって、節約効果は大きく変わります。
例えば、蓄電池だけを導入した場合、夜間に安価な電力を蓄えておき、電気量料金単価が高い日中の時間帯に使う運用によって節約効果を得られますが、日中に電力をあまり使わない家庭では、得られる節約効果が限定的です。
在宅勤務や家族の在宅時間が多い家庭では効果が出やすいですが、昼間に外出している家庭では蓄電池の活用度が下がり、投資対効果が薄れてしまう可能性があります。
無駄とは言えませんが、日中と夜間の電力使用量のバランスによっては蓄電池を導入しても元が取れない場合があると覚えておきましょう。
補助金の有無
蓄電池は高額な住宅設備であるため、導入時に補助金を活用できるかどうかで、元が取れるかどうか決まります。
例えば、国や自治体は、省エネやピークカットを目的とした機器の普及を後押ししており、2025年度には最大60万円の補助が受けられる「DR補助金」がありました。
補助率3分の1、補助額最大60万円の補助金制度のため、初期費用110万円の蓄電池の場合に貰える補助金額は約36.6万円です。
仮に、蓄電容量5kWhで初期費用110万円の蓄電池で「DR補助金」を受けていた場合、初期費用は73.4万円となり、太陽光発電システムとの併用で得られる節約効果を年間41,610円としたら、シミュレーション上では約18年で元が取れる計算になります。
あくまでもシミュレーション上ではありますが、補助金制度の活用によって蓄電池で元を取れる可能性は高いです。
ただし、「DR補助金」は先着順で予算に達し次第終了する仕組みであり、記事執筆時点ではすでに受付が終了しています。
自治体によっては独自の補助制度を設けている場合もあるため、導入を検討する際は最新情報を確認しましょう。
元が取れなくても蓄電池は設置するべき?
蓄電池で元が取れるかどうかは、太陽光発電システムの有無や家庭での電力使用量のバランス、補助金の金額などに影響を受けるため断言はできません。
しかし、元が取れなくても、次の理由で蓄電池の設置を検討するとよいです。
- 売電から自家消費に切り替えたい家庭
- 電気料金単価が高い地域に住んでいる
- ZEH住宅を建設しようとしている
- 防災対策を考えている
それぞれ、順番に解説します。
売電から自家消費に切り替えたい家庭
太陽光発電システムを導入している家庭では、導入後10年間は固定価格で電力を買い取ってもらえる「FIT制度(固定価格買取制度)」が適用されます。
例えば、2015年度に太陽光発電システムを設置した場合、2025年度までは売電価格が33円~35円/kWhで固定されていました。
関西電力の「はぴeタイムR」で最も高い電気量料金単価が28.87円/kWhなことを考えると、発電した電力を消費や蓄電するよりも、売電したほうがお得な期間です。
しかし、FIT期間が終了すると売電価格は大きく下がり、売るよりも自宅で使ったほうが経済的メリットは大きいです。
ただし、太陽光発電システムだけでは日中に発電した電気を夜間まで活かすことができません。
そのため、売電から自家消費へ切り替えたい家庭では、蓄電池やエコキュートなどの住宅機器を導入し、余剰電力を自家消費に回すことが、電気代の削減に直結する有効な手段と言えるでしょう。
電気料金単価が高い地域に住んでいる
電気料金の単価は、契約プランや季節変動だけでなく、住んでいる地域によっても大きく異なります。
特に沖縄電力・北海道電力・東北電力の管内では、大手電力会社の中でも従量電灯プランの電気料金単価が高い傾向があります。
電気料金単価が高い地域に住んでいると、蓄電池だけを導入しても、電気代の節約効果が相対的に大きくなるかもしれません。
日中の高単価な買電量を抑えることで、電気料金の節約につながるため、電気料金単価が高い地域に住んでいる方は蓄電池の導入を検討してみましょう。
ZEH住宅を建設しようとしている
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)住宅とは、断熱性・省エネ性能を高めた上で太陽光発電などを活用し、年間のエネルギー消費量を実質ゼロにすることを目指す住宅です。
光熱費の削減に加え、災害時の電力確保や住宅の資産価値向上といったメリットもあります。
ZEHを実現するためには、蓄電池の存在が不可欠であり、発電した電力を効率よく自家消費する仕組みを整えることが必要です。
建設費は一般住宅より高くなりますが、長期的な電気代の削減と環境配慮を重視する方には、十分検討に値する選択肢になります。
防災対策を考えている
蓄電池の導入を検討するうえで、節約効果以上に注目されているのが「防災対策」としての役割です。
台風や地震による停電時でも、蓄電池があれば照明・スマートフォンの充電・冷蔵庫の運転など、最低限の生活インフラを維持できます。
例えば、蓄電容量が5kWhあれば、LED照明(10W)×5、冷蔵庫(200W)、スマホ充電(10W)を1日8時間ずつ使用した場合でも、2日程度は運用可能です。
発電ができない夜間でも電力を確保できる点は、小さなお子様や高齢者がいる家庭にとって大きな安心材料となります。
防災意識の高まりとともに、蓄電池の価値は年々見直されているため、防災対策を検討している方におすすめです。
家庭用蓄電池の選び方のポイント
蓄電池を選ぶ際のポイントは、主に以下のとおりです。
- 蓄電容量を比較する
- 特定負荷型と全負荷型を決める
- 拡張性を考える
- 長寿命・高サイクルな製品を選ぶ
それぞれ、順番に解説します。
蓄電容量を比較する
蓄電容量とは、太陽光発電で生じた余剰電力や、電力会社から購入した電気をどれだけ蓄えられるかを示す指標で、単位はkWh(キロワットアワー)です。容量が大きいほど多くの電力を蓄えておけるため、夜間の電力使用や停電時の非常用電源として活躍します。
例えば、照明・冷蔵庫・スマートフォン・テレビなどを2日間稼働させたい場合、少なくとも7kWh以上の蓄電容量が必要になると考えられます。
ただし、蓄電容量が増えるほど機器本体の価格が上がるため、無計画に大容量を選ぶのは得策ではありません。
最適な容量を決めるには、家族構成・電力使用のピーク時間・災害対策の重視度など、生活スタイルを踏まえたシミュレーションが不可欠です。
メーカーの公式サイトや販売業者のサポートを活用すれば、実際の使用電力量に応じた具体的な目安を算出できます
自宅の状況に合った容量を選ぶことが、無駄な出費を防ぎつつ、蓄電池を最大限に活かすポイントになると覚えておきましょう。
特定負荷型と全負荷型を決める
蓄電池を選ぶ際には、「特定負荷型」と「全負荷型」のどちらを導入するかを決めることが大切です。
特定負荷型は、停電時にあらかじめ設定した部屋やコンセントにのみ電力を供給するタイプで、冷蔵庫や照明など必要最小限の設備だけをカバーできます。特定の部屋や家電だけ供給するため、電力の無駄遣いを防ぎつつ、コストも比較的抑えられるのが特徴です。
一方、全負荷型は停電時に家全体へ電力を供給でき、いつも通りの生活が維持できる点で安心感があります。
ただし、特定負荷型に比べて初期費用が高額になる傾向があり、無意識に多くの電力を消費してしまう可能性を否定できません。
災害時にどこまでの生活機能を維持したいか、予算や家族構成を踏まえて、両者のメリット・デメリットを比較しながら選ぶとよいでしょう。
拡張性を考える
蓄電池には製品ごとに拡張性の違いがあり、あとからバッテリーを増設できるタイプと、容量が固定されているタイプがあります。
例えば、当初は最低限の容量でスタートし、将来的に家族が増えたり、電力使用量が増加したりした際に、後付けで蓄電容量を増やせる製品であれば、柔軟に対応が可能です。
また、蓄電池よっては太陽光発電やV2H(電気自動車との連携)など、他のエネルギー機器との接続性も異なります。
生活スタイルは年月とともに変化するため、初期導入時だけでなく、将来のライフプランを見越して選びましょう。
長寿命・高サイクルな製品を選ぶ
蓄電池で初期費用を回収し「元を取る」には、できるだけ長く使い続けられることが前提となります。
蓄電池の寿命は「充放電サイクル」で表されることが多く、1サイクルはフル充電からフル放電までで1回と数える仕組みです。
一般的に家庭用蓄電池は4,000〜6,000サイクル(約10〜15年)の耐用年数が目安となっています。
しかし、製品によっては10,000サイクル以上に対応した高耐久タイプも存在し、長期的にみて電気料金の節約効果が持続しやすくなります。
短寿命な製品を選ぶと、導入費用を回収する前に買い替えが必要になる恐れもあるため、信頼性のあるメーカーや長寿命仕様、保証期間などを重視して選ぶことが重要です。
蓄電池の導入を後悔しないために確認したいポイント

蓄電池は「元が取れない」とされる設備ですが、それでも導入に踏み切るなら、後悔しないための判断基準を持つことが重要です。
経済的に元を取りたいと考えるなら、最低でも「太陽光発電システムとの併用」「補助金制度の活用」「電力使用量のバランスが適している」という3つの条件を満たす必要があります。
3つの条件が揃っていないと、費用回収に20年以上かかるケースも珍しくありません。
一方、防災対策や売電からの自家消費切り替えといった目的で導入する場合は、経済性よりもライフスタイルへの適合性が重要です。
家族構成や在宅時間、停電への備え方に応じて、適切な容量や機能を持つ製品を選びましょう。
加えて、太陽光発電システムやエコキュートなどの設備とあわせて検討することで、家庭全体のエネルギー効率を高める選択が可能になります。
まとめ
以上が、蓄電池で元が取れないことに関する解説です。確かに、蓄電池は初期費用の高さや単体での節電効果の限定性により、「元が取れない」と言われがちです。
特に、太陽光発電システムを併設せず、蓄電池単体で運用した場合、電気代の差額だけでは十分な節約効果を得るのが難しく、費用回収には長い年月がかかります。
| 比較項目 | 蓄電池のみ | 太陽光+蓄電池併用 |
|---|---|---|
| 節約単価(円/kWh) | 13.5円 | 22.8円 |
| 1日5kWh節約時の年間節約額 | 約24,637円 | 約41,610円 |
| 初期費用回収の目安年数 | 約44年 | 約18年(補助金適用時) |
しかし、表にあるように太陽光との併用や自治体の補助金制度を活用することで、導入コストを抑えつつ、年間数万円単位の節約につなげることも可能です。
また、売電価格が下がる中で自家消費への切り替えを検討している家庭や防災対策を重視する世帯、ZEH住宅を目指す方にとっては、経済面以外の価値も含めて蓄電池の導入は十分に検討する意義があります。
「エコ突撃隊」では、メーカー正規品を低価格で販売しております。蓄電池や太陽光発電システム、エコキュートなどをお得に導入したいと考えている方は、ぜひご相談ください
参考資料:ソーラーパネルと蓄電池は元が取れる?条件とシミュレーションをご紹介!– solarich(ソラリッチ)公式

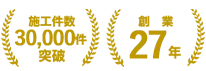






 銀行振込・ローン
銀行振込・ローン