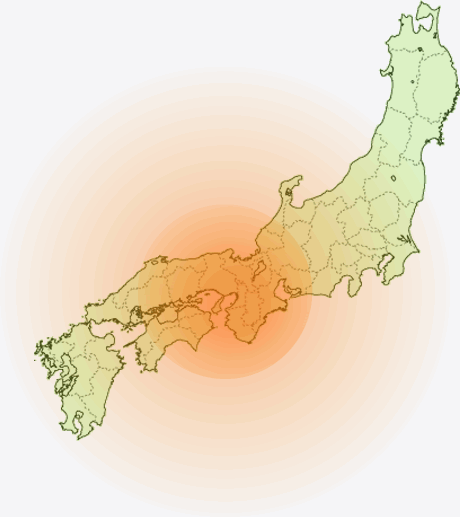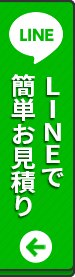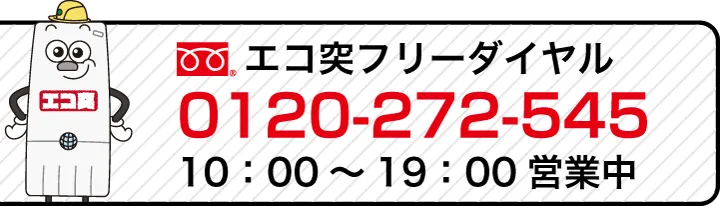オール電化
2025/11/19
エコキュートの室外機がうるさい?原因と静音対策を詳しく解説

夜間や冬場にエコキュートの室外機の音が気になることはありませんか? ご家庭によっては、深夜の運転音が気になったり、隣家との距離が近く、音が反響したりしてしまうこともあります。
本記事では、専門業者の視点からエコキュートの騒音の原因や静音対策、防音・防振の実践方法、さらに交換時期の目安までをわかりやすく解説。静かな住環境を保ち、省エネで快適に使うためのポイントもまとめてご紹介します。
エコキュートの音は室外機から出ている

エコキュートの室外機は、家庭用給湯システムの中心的な機器です。屋外で稼働するヒートポンプユニットが熱を集めてお湯をつくる過程で、運転中には必ず一定の音が発生します。
とくにコンプレッサーやファンが回転する際の低周波音が主な原因で、設置場所や住宅の構造によって聞こえ方が大きく変わります。木造住宅や狭い敷地では反射音が強くなり、隣家との距離が近い場合にはトラブルに発展することもあるのです。
ここでは、音の発生メカニズムと設置環境による影響を詳しく説明し、具体的な静音対策の方向性を示します。
ヒートポンプユニットが発する低周波音
エコキュートの音の主な発生源は、屋外に設置された室外機(ヒートポンプユニット)です。コンプレッサー内部で冷媒を圧縮するときに発生する低周波音(たとえば「ブーン」「シャー」といった音)は、人によって体に響くように感じることもあるようです。
さらに、外気温が低いと圧縮比が上がるため、音の大きさが増す傾向もあります。とくに木造住宅の場合、建物の構造材を通して構造伝搬音として響くことがあります。
設置環境が音の拡散に与える影響
室外機の設置環境は、音の聞こえ方に大きく影響。コンクリート直置きや基礎の傾きがある場合は振動が地面に伝わりやすく、反響音として家屋に戻ってくることがあります。
また、壁面から50cm以内の近接設置では反射音が強まり、隣家の窓方向に伝わるケースも確認されています。対策として、防振ゴムを設置して基礎との接触を緩和したり、吸音パネルや反射防止フェンスを活用すると効果的です。
これらの対策により、体感的な騒音が2〜3dBほど低減することがよくあります。
エコキュートの音は深夜や冬場に大きくなる
エコキュートは、基本的に夜間の電力を利用してお湯を沸かす「深夜運転」が主なため、周囲が静かな時間帯には作動音が目立ちやすくなります。
また、冬場は外気温が低下しヒートポンプの効率が下がるため、コンプレッサーが長時間・高出力で稼働し音が大きくなる傾向にあります。
さらに霜取り運転や冷媒の流れが変化する際に、金属が収縮する音や配管の振動が発生することも。ここでは、季節や時間帯による運転音の変化を理解し、適切な静音対策や機能設定を行うための基本的な知識を解説します。
深夜の沸き上げ運転による作動音
エコキュートは、電気料金が安い深夜帯にお湯を沸かす仕組みのため、この時間帯にコンプレッサーが作動して音が発生します。
とくに冬場は気温が低く、効率が落ちるため、機器がフル稼働し、運転音が増加する傾向にあります。周囲が静かな時間帯であるため、実際の音量以上に大きく感じやすいのも特徴です。
霜取り運転時のカタカタ・コンコン音
低温環境では霜が付着しやすく、霜取り運転時にカタカタ・コンコンという音が出ることもあります。これは一時的なもので、故障ではありませんが、経年劣化で防振ゴムが硬化していると音が増幅しやすくなります。
夜間の動作音が気になる場合は、タイマー設定で運転時間を調整するか、夜間静音モードを備えた機種への買い替えを検討してください。
エコキュートの音がうるさい原因
エコキュートの音が「以前よりうるさくなった」と感じる場合、主に設置環境・機器の経年劣化・基礎や土台の共鳴といった3つの要因が重なっていることも多くあります。
それぞれの原因を切り分けて確認し、状況に合った対策をとることで、無駄な我慢や不要な買い替えを避け、騒音トラブルを軽減できます。
設置環境による反射音・伝搬音
室外機の設置場所や周囲の環境が適切でないと、振動や音が壁や窓に反射し、実際の音量以上に大きく感じられることがあります。とくに隣家との距離が近い住宅や、建物の角・通路側に向けて設置されている場合、反射音が集中しやすく、注意が必要です。
また、宅地が狭い場合や建物が密集している地域では、音が逃げにくくなるため、体感騒音が増加します。このようなケースでは、設置位置の見直しや向きの調整、防音フェンスの設置などで音の伝わり方をコントロールすることが効果的です。
経年劣化による振動・異音
10年前後使い続けたエコキュートでは、ファンモーターやコンプレッサーの軸ブレ・摩耗・ベアリングの劣化などが進み、「ゴー」「ガタガタ」といった異音が出やすくなります。
最初は小さな音でも、部品の傷みが進行すると振動が大きくなり、深夜の静けさの中ではとくに気になるようになります。運転音が急に変化したり、金属のこすれるような音が続いたりする場合は、故障の前兆である可能性も考慮しましょう。
このような症状がある時は、早めに専門業者に点検を依頼し、部品交換や本体交換の必要性を確認することが重要です。
基礎や土台の共鳴による増幅
室外機を載せているコンクリートブロックや架台、バルコニーの床材などの土台部分が共鳴板のような役割を果たし、振動を増幅してしまうケースもあります。
とくに薄いコンクリートや鉄骨製の架台は振動を拾いやすく、建物の梁や柱を通じて家全体に音が伝わる「構造伝搬音」となりやすいのが特徴です。
その結果、実際の騒音レベル以上に「家全体が響いている」ように感じてしまいます。こうした場合は、防振ゴムの追加や架台の補強・交換、土台と建物を絶縁する工事などで共鳴を抑えることが有効です。
必要に応じて、次の防音・防振対策で紹介する方法を組み合わせて検討しましょう。
エコキュートの音を抑える防音・防振対策

ここでは、エコキュートの騒音を抑えるための実践的な方法を紹介します。防音材の中でも、ポリエチレンフォーム製の吸音パネルや防水カバー併用のグラスウールシートは効果が高く、音の反射や振動を同時に軽減することが可能です。
また、壁面や基礎に施工する遮音マット(EPDMゴム製)を併用することで、住宅全体への伝搬音をさらに抑えることができます。これらの素材は屋外使用にも対応しており、耐水性や耐候性にも優れているため、長期間にわたり防音効果が期待できます。
防振ゴム・防音シートの設置
音を軽減するには、防振ゴムの設置がもっとも手軽で効果的です。機器の下にゴムを敷くことで、振動が地面へ伝わるのを防ぎます。また、壁面に防音シートや吸音パネルを取り付けると、反射音を減らせます。
設置位置と角度の見直し
隣家との距離が近い場合は、室外機の向きを変更するだけでも改善されることがあります。さらに、配管固定金具の緩みや基礎のひび割れも音の原因になるため、年に1回程度の点検がおすすめです。静音性を重視する場合は、静音設計のエコキュートへの買い替えも一つの選択肢です。
10年以上経過したエコキュートは交換のサイン
エコキュートの交換を検討する際には、補助金制度の金額目安や申請期間、地域による制度差も押さえておくとよいでしょう。たとえば、国の「省エネ住宅支援事業」では最大13万円前後、自治体によっては3〜5万円程度の助成を受けられるケースもあります。
募集期間は年度単位で設定されることが多く、早期終了となる場合もあるため、設置を決めたら早めの申請が重要です。地域によって補助対象機種や申請方法が異なるため、自治体の公式サイトや販売施工店に確認することをおすすめします。
異音や漏れは老朽化の兆候
エコキュートの寿命はおよそ10〜15年です。経年劣化が進むと、異音・水漏れ・湯圧低下などの症状が現れます。部品交換や修理費が多くかかる前に、省エネ性能の高い最新機種に切り替えることで、光熱費を抑えながら静音性も向上させることができます。
補助金を活用してお得に交換
多くの自治体では、エコキュートの交換・導入に補助金制度が設けられています。申請期間や条件は地域ごとに異なるため、最新情報を確認の上、適切に活用してください。
エコキュートを交換するならエコ突撃隊へ
古くなったエコキュートの交換を検討している方は、地域密着型で実績豊富なエコ突撃隊にお任せください。これまでに数百件以上の交換・設置工事を手がけており、各地域の住宅事情や気候条件を熟知しています。
メーカーを問わず対応が可能で、パナソニック・三菱・日立・ダイキンなど主要メーカー製品の交換実績も豊富です。
施工前には現地調査を行い、防音・防振施工を含む、最適な設置プランを提案。さらに、自治体や国の補助金申請のサポートにも対応しており、費用を抑えつつ、静音性と省エネ性の両立が可能な最新モデルへの交換もご提案いたします。
地域で信頼されている専門チームとして、迅速で丁寧な工事や充実したアフターサポートにより、快適な住環境をお届けします。

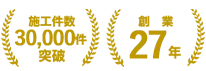






 銀行振込・ローン
銀行振込・ローン