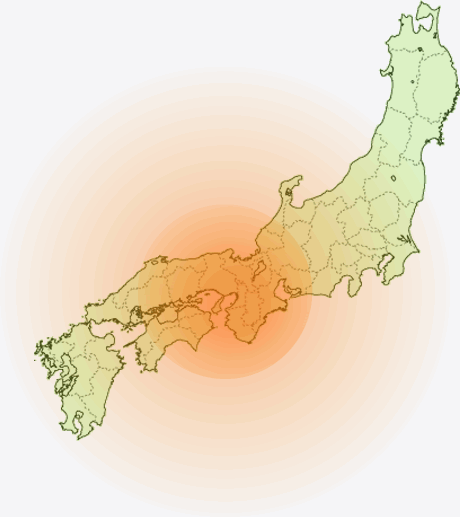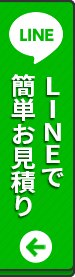蓄電池
2025/11/19
【2025年最新版】蓄電池の今後を徹底予測!蓄電池の最新動向と賢い導入ポイント
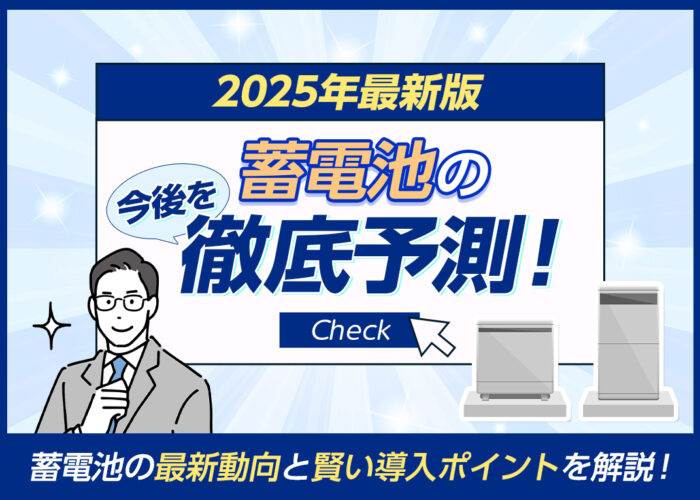
近年、電気代の高騰に頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。また、大きな災害も頻発している昨今、災害への備えは他人ごとでありません。さらに環境意識の高まりによって、環境に負荷を与えない生活を意識する人も増えています。そのような背景で今注目を集めているのが、蓄電池です。ところが蓄電池を導入するには高額な費用がかかるため、蓄電池を導入して得られるメリットを今後も享受できるかどうかは、非常に重要なポイントです。そこでこの記事では、蓄電池の役割や仕組みといった基本情報から、蓄電池の今後の動向まで、詳しく解説していきます。
1.そもそも「蓄電池」とは?
まずは蓄電池の役割と仕組みや活用方法など、蓄電池の基本についておさえましょう。
1-1.家庭用蓄電池の役割と仕組み
蓄電池は、電気をためておく装置です。蓄電池にためた電気をある程度使ったら、再び新たに電気を蓄えられるので、何度も繰り返し使える「電池」のような役割を果たします。
家庭用蓄電池は、電気をためる蓄電ユニットや、直流電流を交流電流に変換するパワーコンディショナーなどで構成されています。放電する際には、マイナス極の金属が電解液に溶け出して、電子がプラス極に移動し電力を発生させる仕組みです。充電する際には放電と逆方向に電気を流し、マイナス極で再び化学反応を起こすことで、放電と同じ状態に戻します。
1-2.蓄電池の基本的な活用法とは?
蓄電池は、たとえば夜間の安い電気をためておけば、単価の高い時間帯に蓄電池の電気を使うことが可能です。
また、太陽光発電で発電した電気をためておくのに購入する人も多くいます。太陽光発電で発電した電気は、その場で使わなければためておくことはできません。そのため、日当たりの良い日中に発電できたとしても、日中家族が不在の場合は無駄になってしまいます。そのため、余った電気は電力会社に売る方法が多く採用されていたものの、一定期間お得に買取してもらえる「固定価格買取制度(FIT)」の期間が終了後は、売電のメリットもそれほど大きくはありません。そこで、日中発電して使い道のない電気を、売電せずに自分の家で使えるように、蓄電池にためておく人が増えています。
どちらの使い方も、電気代を節約することが可能です。
1-3.蓄電池は災害時にも大活躍
蓄電池は災害時に停電が発生した時のライフラインとして、絶大な効果を発揮します。蓄電池があれば、停電時にも照明や冷蔵庫、Wi-Fiルーターやスマホの充電など、最低限の生活に必要な電力を確保できるのです。
1-4.太陽光発電と組み合わせてさらに広がる使い方
蓄電池は、太陽光発電システムと組み合わせることで、最大限の効果を発揮できます。日中発電した電気を無駄にすることなくためて、夜間や悪天候時に活用すれば、電気代を大きく削減できます。また、常に日中発電した電気をためておくようにすれば、突然の停電時にも慌てることなく、電気を確保できるのです。このようにコスト面でも利便性の面でも、太陽光発電と蓄電池の組み合わせは、最も理にかなっていると言えます。
2.なぜ今、蓄電池が注目されているのか?
ここからは、なぜ蓄電池が注目されているのか、その理由についてみていきましょう。
2-1.電気代の高騰はこれからも続く見込み
近年、電気代は高騰を続けており、家計に大きな打撃を与えています。とくに日本のエネルギー自給率は2022年で12.6%と大変低く、海外からの輸入に頼っているため、燃料価格の高騰や円安などの影響を受けて安定しません。
電力消費のピークは、夏場は13時から16時、冬場は8時から11時、および年間を通して17時から20時頃です。このピークの時間帯に電気消費を抑える工夫が必要なものの、昼間の電気料金は高めに設定されているケースが大部分です。蓄電池を活用すれば、ためておいた電気を使うことで単価の高い時間帯に電気を買う量を減らし、電気代の削減につながることが期待できます。
2-2.再生可能エネルギーの拡大と蓄電池の役割
石油や石炭とは異なり、繰り返し利用できて発電時に二酸化炭素をほとんど排出しない、風力や太陽光といった再生可能エネルギーが注目を集めています。そしてこの再生可能エネルギーが広まるほど、「発電した電気をどのように使うか」「余った電気をどのように無駄なく活用するか」が課題になってきます。蓄電池は、発電した電気をためておけるので、再生可能エネルギーを生活に取り入れるために、必要不可欠です。とくに最も身近な再生可能エネルギーである太陽光発電を導入している家庭の場合、発電量と消費量のバランスをとるのに蓄電池が有効になります。
2-3.停電時・災害時の備えとして
近年、日本において大きな自然災害が頻発しており、各家庭において災害時の備えに対する意識が高まっています。防災意識の高い家庭では、単なる電気機器としてではなく、暮らしの「保険」として蓄電池を導入しています。
万が一、停電になってしまうと、冷蔵庫が止まって食料の確保が難しくなったり、スマホの充電ができず外部と連絡が取れなくなったりと、大きな支障が生じてしまうものです。蓄電池があれば、停電時にも最低限必要な電気が確保できます。
3.今後どうなる?蓄電池の最新動向
ここからは、蓄電池の動向について、今後どのように展開していくのか予想していきます。
3-1.国内外で広がる蓄電池のニーズ
日本国内において、家庭用・業務用を問わず、蓄電池の需要が拡大しています。2023年度の蓄電池の出荷台数は約15.6万台であり、前年度比125%を記録しました。2019年以降、蓄電池の出荷台数は毎年10万台を超えていて、日本における蓄電池の需要が伸びていることが分かります。
また、世界的にも再生可能エネルギーの普及や電気自動車の広まりなどから、蓄電池の市場が急速に拡大していると言われています。
3-2.2030年・2050年のエネルギー計画における蓄電池の役割
日本では、「電気をためて使う」「再エネを主力にする」ことで、2030年および2050年の日本のエネルギー計画実現を目指しています。2030年は、政府の掲げる「温室効果ガス46%削減(2013年度比)」の目標年です。再生可能エネルギーを電源構成の3割から4割にまで高めて、太陽光発電・風力発電を安定活用するために、家庭・地域における蓄電池導入の促進が重視されています。
さらに2050年は、日本が「カーボンニュートラル(温室効果ガス排出実質ゼロ)」を実現する目標年です。再生可能エネルギーを中心にした電力供給を定着させるとともに、電気自動車や蓄電池などエネルギーの「地産地消」が当たり前になる社会を目指しています。このためにも蓄電池は重要な役割を担っており、今後は蓄電池の容量や性能のさらなる向上が進められていくでしょう。
このように、温室効果ガス削減目標やカーボンニュートラル達成のために、蓄電池は欠かせない存在です。
3-3.蓄電池のコスト低減・技術革新がもたらす変化
蓄電池の価格は、年々低下傾向にあるのはご存じでしょうか。蓄電池といえば、便利なものの値段の高さがネックでした。ところが蓄電池に使用されるリチウムイオン電池の性能が向上し、製造プロセスも効率化されてきたことにより、生産コストが削減されつつあるのです。電気自動車が普及したことによる大量生産も、コストを下げる一因となっています。蓄電池の需要が高まり、市場が活性化したことで販売競争も激化しているのも、価格の低下につながっているのでしょう。
2017年度には約26万円/kWhだった蓄電池の価格が、2019年度には約19万円/kWhにまで下がっているとも報じられています。また、経済産業省は2030年に約7万円/kWhという目標価格も設定しており、今後の技術進歩による蓄電池の量産化・材料コスト低減が期待されるでしょう。
3-4.家庭・企業・地域で広がる、蓄電池の新しい使い方
蓄電池は、各家庭だけではなく、企業や施設、そして地域全体でも使われ始めています。たとえば電力ピーク時のコスト削減や災害時の備え、地域のエネルギー自給自足の仕組みとして、蓄電池が注目されているのです。また、企業・地域としても脱炭素に向けた取り組みは避けて通れないものとなっているのも、蓄電池の導入が増えている要因でしょう。企業・地域向けの大規模な系統用の蓄電池や、工場向けの蓄電池の需要が高まり、一般家庭以外にも用途が広がることで、普及は拡大しています。
4.蓄電池の普及率と、今後の展望
ここからは蓄電池の普及率について、現状と今後の予想をお話していきます。
4-1.日本の家庭で蓄電池はどれくらい普及している?
現在、日本における家庭用蓄電池の普及率は、約5%にとどまっています。これは、太陽光発電システムの普及率が約10%なのと比較すると、約半分です。それでも、2011年以降、蓄電池の出荷台数は大幅に伸び続けてきました。とくに2011年からのわずか6年間は、約25倍も増加しているのです。これは、2011年に起きた東日本大震災によって、災害への備えに蓄電池が有効だと知った人が非常に多かったのでしょう。
4-2.日本の家庭における蓄電池普及の特徴とは?
現在蓄電池は約5%の普及率であるものの、これは地域差などが大きく、たとえば都市部の普及率が高い傾向にあります。また、蓄電池を単体で導入する人は、蓄電池を導入した家庭全体の約40%程度であり、太陽光発電と同時に導入した家庭は約60%です。新築時に蓄電池を導入した家庭は約30%にとどまり、全体の約70%は既存住宅に後付けしていることも分かっています。これは、先に太陽光発電を設置している家庭が、蓄電池を追加で導入している家庭が多いこと、災害対策で後から導入した家庭が多いことを要因とするものでしょう。
太陽光発電が普及し始めた2010年代前半においては、作った電気は電力会社に売る方が得だったものの、固定価格買取制度の開始から10年以上たった現在では、買取価格は大幅に下がりました。そのため、自分で使った方が経済的な状況になっているため、蓄電池の普及は今後も増えることが予想されるのです。
4-3.蓄電池普及が進まない理由と、これから変わるポイントとは?
蓄電池の普及率がまだまだ低めである背景には、いくつかの理由があると考えられます。まず、大きな要因は、設置費用の高さでしょう。家庭用蓄電池の価格は、5〜10kWh程度の容量のもので約100~200万円ほどです。そのため、すでに太陽光発電を導入している家庭でも、安くなるまで導入を見送っている傾向にあります。
また、設置スペースの確保も課題です。戸建て住宅であっても設置場所に余裕のない場合や、屋外への設置が難しい環境においては、蓄電池の導入をためらうケースが見られます。特に都市部の狭小住宅においては、この問題が顕著に見られます。
さらに、補助金制度についての理解不足も、蓄電池普及率の上がらない要因の一つです。実際には国・地方自治体で蓄電池向けの補助金制度を用意しているものの、補助金の存在自体を知らない、どのような補助金なのか知らない、申請が難しそうといった理由で、蓄電池導入に踏み切れない家庭も少なくありません。
ところがこのような課題は、今後解消に向かうことが予想されます。購入ではなくリースやサブスク型などのサービスも登場しており、初期費用ゼロで蓄電池を導入できるサービスが登場しているのです。また、蓄電池のサイズも壁掛け型や薄型タイプなどが登場しており、今後もスリム化・コンパクト化が進むと予想されます。補助金についても、今後も拡充していくことが予想されるので、初期費用が高いという蓄電池のネックを解消する効果が期待できます。
4-4.補助金を活用すれば導入ハードルはぐんと下げられる
蓄電池はどうしても初期費用がかかってしまう点で、導入を見送っている人も多いのではないでしょうか。ところが、各家庭の蓄電池導入を促進するために国・自治体が用意している補助金を利用できれば、初期費用を大きく抑えられるのです。
国の補助金には、たとえば「DR家庭用蓄電池事業(通称「DR補助金」)」では、家庭用蓄電池を導入すると最大60万円の補助(額は2024年度・2025年度のものであり、年度によって額は変動)が受けられます。また、「子育てグリーン住宅支援事業」では、蓄電池を導入する子育て世帯などに対して、一律64,000円程度の補助(年度によって額は変動)をしている実績があります。
さらに、「防災対策」や「再生可能エネルギー普及支援」の一環として蓄電池設置を助成する自治体も少なくありません。たとえば東京都では「家庭における蓄電池導入促進事業」として、蓄電池の容量に応じた助成を行っています。太陽光併用住宅の場合、1kWh当たり数万円から数十万円(上限数十万円)の補助が受けられる例もあります。自治体によっては国の補助金と併用できるケースも多く、よりお得に蓄電池を導入できるのです。
5.今後、蓄電池を導入するメリットとは?
今後、蓄電池を導入するには、多くのメリットがあります。そのメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
5-1.今後さらに進化していく蓄電池の性能
近年の蓄電池は、従来のものと比較して小型化・高性能化・長寿命化へと大きく進化しています。これまではリチウムイオン電池が主流だったものの、それに加えてより劣化しにくく安全性の高いリン酸鉄リチウム電池なども普及が進んでおり、長く使える製品が増えてきているのです。
さらに注目されているのが、「AI」や「IoT」による賢い電気の使い方に、蓄電池を取り入れる方法です。たとえばAI搭載の蓄電池システムなら、天気予報や時間帯ごとの電気料金を自動で分析して、蓄電するタイミングや使用するタイミングを自動で最適化してくれます。たとえば、昼間は太陽光で発電して余った電気をためておき、夜間電気代の高い時間帯に自動で使用するといったお得な使い方を、手間をかけずにかなえてくれるのです。また、IoTを連携できる蓄電池なら、スマホから簡単に操作できるのも魅力です。外出先からもアプリで蓄電の状況をチェックできたり、家事の合間に天候を見ながら充電量を設定したりと、気軽にコントロールできます。
将来的には、冷蔵庫やエアコンといったほかの家電と連動し、自動で電力を最適に分配するシステムも普及していくと予想されています。
5-2.蓄電池の補助金制度は今後も拡充の方向へ
家庭用蓄電池の導入を強く後押ししているのが、国や自治体の補助金制度です。環境省・経済産業省による「再エネ・省エネ支援事業」は毎年のように実施されている実績があり、2025年以降も再生可能エネルギーの普及を目指して、補助制度は継続され、拡充されることも大いにあり得ます。とくに、太陽光発電とセットで導入する家庭に対する手厚い支援は、大いに期待されるところです。
自治体によっては、国の補助金と併用できるケースも多々あり、実質的に蓄電池の導入費用の3割から5割程度補助を受けられることもあり得ます。申請手続きは蓄電池の販売店や施工会社が詳しく、申請を代行してくれることも多いので、難しそうだと敬遠せずに、まずは地域の補助金制度をチェックしてみましょう。そして施工会社や販売店に、気軽に相談してみるのがおすすめです。
補助金は、毎年の予算額が上限に達し次第終了してしまうので、早めの申し込みが重要です。同じ製品でも、補助金を受けられるかどうかで負担額は大きく異なります。いずれ蓄電池を導入したいと検討しているなら、補助金を受けられるタイミングで購入するといいでしょう。
5-3.今後の価格動向
蓄電池の開発・製造技術の進歩によって、蓄電池の価格は下がりつつあります。とくに次世代バッテリー技術が実用化されれば、価格面でも大きな変化をもたらすでしょう。そして、電気自動車の普及で量産されれば、価格の低下も加速することが予想されます。
5-4.家計にも安心をもたらす「実利」の数々
蓄電池を導入すれば、もしもの停電時に照明や冷蔵庫といった家電が使える安心感はもちろん、日々の節電にもつながります。昼間に太陽光発電で作り出した電気をためておいて夜間に使えば、電力会社から買う電気の量を大幅に減らせます。さらに電気代の高いピーク時間帯に電力会社から買うのを避けるよう自動制御してくれる機種もあって、無理なく節約が可能です。
夜間の安い電気を蓄電池にためて昼間に使うだけで、年間数万円の節約になるケースもあります。とくに電気の使用量が多い家庭や、オール電化住宅において、その効果はより実感しやすいでしょう。
5-5.蓄電池の初期費用は10~15年で回収できる試算
電気代の高騰が続く中、少しでも毎月の負担を減らしたいと考える家庭は多いでしょう。蓄電池を導入する最大のメリットは電気代の削減効果です。たとえば4人家族で月の電力使用量が500kWhだと仮定すると、月の電気代は16,500円だと試算できます。そして10kWhの蓄電池を導入して、夜間の安い電気を充電して昼間に使用したとすると、計算上1か月の電気代削減額は約3,000円・年間削減額は約36,000円になります。
10kWhの蓄電池を導入する初期費用は、機器代金約180万円の他に諸経費や設置工事費など含めて合計約230万円、東京都の補助金例でおよそ95万円の補助を受けたとしても、実質負担額は約135万円です。年間の電気代削減額と売電ロスの回避額を合計した年間メリットを約5万円と仮定すると、初期費用を回収するには、27年かかってしまう計算になります。
しかし太陽光発電と併用した場合は、月額約13,450円・年間約16万円と、蓄電池単体の5倍以上の節約が期待できるようになるのです。この場合、初期費用の回収期間を10年短縮できる計算になります。そのほかにも電気代の値上げなどを総合的に判断すると、実質的な初期費用の回収期間は10~15年程度だと言われています。
6.まとめ
蓄電池は、節電効果はもちろん、災害時の備えや環境貢献にもなる頼もしい設備です。導入するには初期費用が高額なものの、補助金を活用すれば負担を減らせ、10年ほどで回収できるケースも少なくありません。今後はさらに技術の進化と価格の下降、制度の充実が進むことが考えられます。蓄電池を導入することで得られるメリットをより多く受けるには、早期に導入するのが最善策です。
蓄電池の導入をお考えなら、「エコ突撃隊」にお任せください。最新蓄電池を多数取り扱っており、家庭の電力使用状況や太陽光発電との相性などを丁寧に診断したうえで、最適な1台をご提案いたします。さらに設置工事や補助金申請のサポートまでワンストップで対応いたします。電気代の高騰や停電時の備えについてお困りの方は、まずは無料見積もりからお気軽にお問い合わせください。

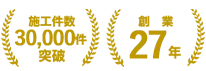






 銀行振込・ローン
銀行振込・ローン